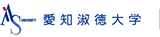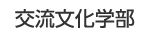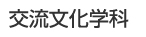-

フィールドワークで訪れたモンゴルのヒンデル村での写真。一緒に写っているのは現地を案内してくださった方。
- Q.大学進学の際にモンゴル語学部に進学したそうですが、なぜモンゴル語の勉強をしようとされたのですか?
- 当初、モンゴル語は全く視野に入っていませんでした。しかし、自分が何を学びたいのかを考える中で、他にはないユニークな分野に挑戦したいという気持ちが湧きました。それでモンゴル語学科に進むことにしたのですが、漠然とした気持ちで入ったため、入学後は大変でした。モンゴル語の文法は日本語に近いところがあって学びやすい面もありましたが、発音が難しく、特にリスニングに苦労しました。留学前には、ネイティヴの先生が言うことがほとんど理解できなかったですね。今振り返っても、学部時代は劣等生でした(笑)。
そんな私が4年生の時にようやく勉強に興味を持ち始めました。不思議なことに、自分が就職活動をして企業で働く姿が全く想像できなかったんです。それで、家族の支援もあり、勉強を続けることに決めました。ただ、少人数の学科でもう一人同じ先生の研究室を目指していた同級生がいたので、大学院試験では猛勉強しました。この勉強を通じて、ウイグル式蒙古文字で書かれている文献をある程度読めるようになりました。
- Q.モンゴルでのフィールドワークでは、どのような体験をされたのですか?
- 修士課程では外務省の交換留学生制度を利用してモンゴル国立大学に1年、その後、博士課程では文部省のアジア諸国派遣留学生制度を用いて2年間留学しました。モンゴルでは英雄叙事詩が今も口頭で伝承されているイメージがあるかもしれませんが、実際にはそうした伝承はあまり残っていません。そのため、研究の中心は記録され文献化された伝承になります。ただ、文献を中心としているからといって、フィールドワークが不要というわけではありません。記録された伝承をめぐる慣習や、人々がそれをどう認識しているのかを探る手段として、フィールドワークは欠かせません。博士課程で対象にした叙事詩の場合、伝承者が生存していましたが、どの伝承者からどのような伝承を受け継いだのか、その伝承をどのように認識していたのかなど、テキストの位置づけに関わる聞き取り調査をすることが多かったです。
フィールドワークでは、ときに予想外の出来事やユニークな交渉を経験することもあります。例えば、アルタイ・ウリヤンハイ部族の有名な伝承者に会いに行った際には、「タルバガン(シベリア・マーモット)を狩りに行くので、一日に狩れるマーモットの頭数から取れる革代金を支払ったら話を聞いてやる」と言われました。仕方なく代金を支払い、ようやくお話をうかがえたのは今でも忘れられない経験です。
このように交渉を通じて得られる話も貴重でしたが、同時に現地の文化遺産意識が高まりつつある時代背景も感じました。例えば、役場の文化担当者が突然やってきて、活動内容を確認されることもありました。当時は、英雄叙事詩が文化遺産として重要視され始めた時代であり、外国人が直接伝承を記録することには慎重な姿勢がとられていました。それでも、抜け道もあり、工夫次第で調査が可能な場面もありました。このような状況下で、叙事詩をめぐる作法や伝承者たちの認識についての聞き取りが主な調査内容となり、それが貴重なフィールドワークの成果として研究に結びつきました。
- Q.現在藤井先生はフィールドワークより文献研究の研究を主にされていますが、移行された理由は何ですか?
- 文献研究が主流であるということに加え、研究対象を英雄叙事詩から『元朝秘史』へと移したためです。この文献はチンギス・カンの祖先からオゴデイ時代までをカバーする歴史的文学作品で、英雄叙事詩的な視点で新たな研究の可能性を感じています。

2009年に開催された第16回文化人類学・民族学国際シンポジウムでの登壇の様子。
- Q.これまでで特に印象的と思われる成果は何でしょうか?
- 博士論文で、英雄叙事詩に登場する特殊な数字がチンギス・カンの即位年である“1206年”と密接に関連していることを発見したことです。これまで、叙事詩に登場する人物の名前は歴史上の人物とは直接的な関連がないと考えられていましたし、叙事詩には出来事が生じた年も直接的には言及されません。そのため、この発見は叙事詩と歴史的出来事の関連性を示唆する重要な論点となり、『元朝秘史』を英雄叙事詩的観点から研究する可能性を開くきっかけになりました。
- Q.フィールドワークと文献研究、それぞれの魅力はどこにあると思いますか?
- この2つの手法は対立するものではなく、むしろ相互に補完し合う関係にあると感じています。フィールドワークでは、現地でしか得られない貴重な気づきを得られるのに対して、文献研究では、記録を読み解くことで新しい発見や深い理解が得られます。それぞれ異なる魅力がありますが、特にフィールドワークでは下調べをし、自分なりの問いを持って臨むことが大切です。また、可能であれば複数回訪れることで、より深く現地を理解できます。私自身も1回目では見えなかったものが、2回目でようやく理解できることがよくありました。それがフィールドワークの醍醐味ですね。

台湾フィールドスタディへサポートとして参加した際の写真。2005年に愛知淑徳大学に赴任し、様々な先生のフィールドスタディに参加してきたそうです。
- Q.フィールドワークを通じて得られるものは何でしょうか?
- フィールドワークでは、自分のアンテナに応じて現地の現実が見えてきます。事前の知識や関心を持つことで、現地での体験がより豊かになるんです。例えば、沖縄や台湾でのフィールドスタディに参加させていただいた際には、主催の先生方が限られた時間の中で、どのように学びの場を作り上げているかを実感しました。同僚の先生方から学ぶ貴重な機会となり、本当に良かったと思っています。
- Q.最後に、学生へのメッセージをお願いします。
- 学生時代は、成功だけでなく、失敗や葛藤を経験することが何よりも価値ある財産になります。私も、モンゴルでのフィールドワークや文献研究に挑む中で、多くの困難に直面しましたが、そのたびに異文化の奥深さに気づかされました。異なる文化や価値観に向き合う経験は、自分の世界を広げるだけでなく、人と人とをつなぐ力になります。焦らず、自分らしいやり方で挑戦を続けてください。